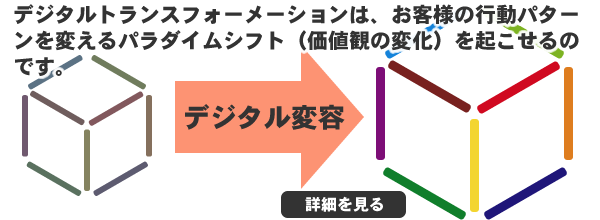魏志倭人伝や後漢書で述べられている邪馬台国連邦に所属する遠方の国々について
2023年8月5日
魏志倭人伝や後漢書で述べられている邪馬台国連邦に所属する国のうち、遠方で詳細の不明な国々について、これらを明らかにすることにより、邪馬台国の大きさがわかる。(九州北部からどこまでが邪馬台国連邦なのかという問い)
・国名の読み方が判明した。
・漢字には、呉音、漢音、唐音、慣用音、訓読みの5音があるが、文字の発音(読み)は、六朝時代(222年〜589年)の呉音を用いるべきである。
・国の直前の「奴」は「ぬ」と発音し、「の」の転訛である。
・王の名の末尾の「呼」「乎」は、呉音にて「を(Wo)」と発音し、「おう」である。
・各国は、詳細が不明なので南から北に並んでいない。
・中国人の訛りを考慮
五十音のうち、次の音は中国語にはない音。(中国の人には発音しづらい)
き、け、こ、せ、そ、て、の、ひ、へ、め
・8世紀、律令制以前(遅くとも西暦500年には成立していた。)から存在した日本の旧国名
沖縄、北海道、は含んでいないものだが、日本広しといえども、たった9国しかなかった。
豊国 大分 とよ
筑紫国 福岡 ちくし 上古、港から迎賓館まで石畳を敷設していたのが国名の由来
火国 熊本 ひ
総国 千葉 ふさ 7世紀藤原京出土木簡は上総、上古はかずさ(かぬさ)が先か、毛の国(群馬)も「こうずけ」が先か
凡河内国 大阪 おおしこうち
丹波国 京都 たにわ
越国 新潟 こし
吉備国 岡山 きび 上古4つの国の総称は「備(び)」
常陸国 茨城 ひたち
(邪馬台国連邦)
次有斯馬國、 すま すみ 大隅半島 鹿児島東部
次有已百支國、 いすき いぶすき 指宿 鹿児島
次有伊邪國、 いや いよ 伊予 愛媛
次有都支國、 つき とき 土岐 岐阜南東部
次有彌奴國、 びぬ びのくに 吉備 岡山 上古4つの国の総称は「備(び)」
次有好古都國、 こごうつ こごうち 小河内村 東京 奥多摩
次有不呼國、 ふおう すおう 周防 山口
次有姐奴國、 そぬ そのくに
次有對蘇國、 つさ とさ 土佐 高知
次有蘇奴國、 さぬ さのくに 讃岐 香川
次有呼邑國、 おおし 凡河内 おおしこうち 大阪
次有華奴蘇奴國、 かぬさぬ かぬさのくに 上捄 上総 かぬさ 幣 麻 ふさ 総 千葉東南部 律令以前からかずさ<かぬさ>(藤原京木簡)
次有鬼國、 き 紀州 和歌山
次有爲吾國、 なご 名古屋 愛知
次有鬼奴國、 きぬ きのくに(重複)
次有邪馬國、 やま
次有躬臣國、 みお みの 美濃 岐阜中部
次有巴利國、 はり 播磨 兵庫
次有支惟國、 きし こし 越 新潟
次有烏奴國、 うぬ うのくに 羽 山形
次有奴國。 ぬ の
(邪馬台国尽きるところの南にある競合国)
狗奴国 くぬ けぬ けのくに 毛の国 群馬 中国人には「き」と「け」は発音しづらい
(王の名)
卑弥弓呼 ひびきおう ひにきおう ひのもとおう 日の本王
卑弥呼 ひにおう ひのおう 火の王
・まとめ
九州北部から南部の九州全域から中国四国を経て、近畿、中部、信越、関東南部、東北西部まで、が倭と呼ばれた、邪馬台国連邦の緩やかな支配地域であった。
そして、競合国(敵対国)は、関東北部、毛野国であったのである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち