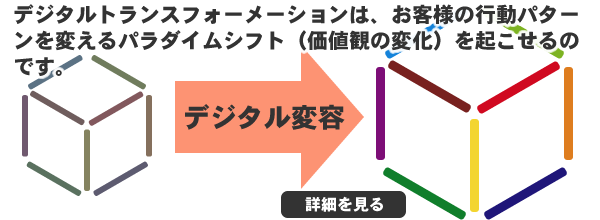縄文展〜火焔土器など縄文土器の模様は海や湖の波と川の流れの意匠だった
20180827
火焔土器の意匠についての新説

縄文展
火焔土器が見れるというので、東京国立博物館へ。
火焔土器は、日本の新潟でだけ見つかっている5000年前のポット。
縄文展では、10センチから20センチぐらいまで土器に近づいて、細部まで観察することができた。
これほど近くで、火焔土器などの縄文土器を見れてとても楽しかった。
縄文土器は、芸術性が高く、見ている者を圧倒するようなチカラを感じた。
他にも縄文のビーナスや遮光器土偶も見ることができた。
土偶については、すべての土偶が女性で、かつ妊婦さんを意匠化したものだった。
土器については、多くの土器で「縄目」が意匠化されているが、それは一般的に言われている「稲などの植物をなった縄を押し付けて模様とした」のではなく、土器表面を彫刻のように削ったり、あるいは粘土を盛り上げることで「縄目」のような模様を形成していることがわかった。
そして、この縄目などの「線状の意匠」は「海や湖の波と川の流れ」を表現していることがわかった。
「水」は動植物などすべての生き物が存続するために最低限無くてはならない生命の糧であり、川や海から魚や貝などの海産物という恵みを受けることもできる。
日本人にとって、「やま」が雨ごいとしての信仰対象であるのと同じように、山から流れる川や湖の「みず」は現在人の「カネ」に相当するような「とても大切なもの」だったのである。
火焔土器を含む縄文土器には、これでもかとストリング(線状の意匠)が刻まれたり、盛り上げられたりしていた。
火焔土器の炎のような意匠は、「日本海の荒れた波」を表したものだったのである。
多くの土器の用途は、煮炊き以外にも、生活用水を汲み置きしておくためのポットであった。
絵柄などの意匠によって、その器の用途をわかりやすく表した。
・煮炊き用鍋
- 煙の意匠、底が鋭角
・水がめ
- 水の意匠
・果実酒醸造用ポット
- 植物のつるの意匠
果実や米などの保存には土器ではなく、通気性の良い植物のつるや皮で編んだ袋を利用した。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち