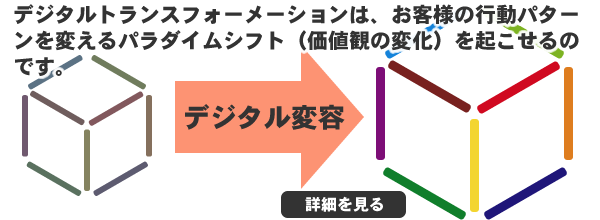カタカナがあるのになぜひらがなを作らなければならなかったのか?
カタカナがあるのになぜひらがなを作らなければならなかったのか?
カタカナもひらがなも両方とも平安時代に考案されたことになっている。
イメージ的には、カタカナは法令などの公文書に用いられる印象がある。
対して、ひらがなは万葉仮名から派生した文字なので和歌や俳句で使われる印象がある。
和歌を歌う歌人たちが、カクカクしたカタカナを嫌がってわざわざ独自に文字を作ったとでも言うのだろうか?
アルファベットにも大文字と小文字があるが、大文字は文章の初めや強調したい箇所などに用いる。
日本語のアルファベットにあたる「かな」がなぜ二種類あるのか納得できる説明は存在しない。
ついこの間まで、私は言葉の語源を判断するのに、その言葉を漢字で書いた時のそれぞれの漢字個々の意味から導き出そうとしていた。
そう言う人がほとんどだと思う。
何しろ、漢字が伝来した3世紀ごろまでは日本人は文字を全く使っていなかったと学校で教わってきたからだ。
しかし、数十万年前の洞窟画が残っているということは筆記具は古くからあった。
日本語には「つづる」「したためる」など、漢字を音読みしたのではない「やまとことば(訓読み)」の文字を書くという意味の単語が存在する。
文字を持たない会話だけの社会になぜ文章を書くという意味の単語があるのか?
部→へ、由→ユ、良→ラ、和→ワ、恵→ヱ、乎→ヲ
など明らかにおかしな文字の起源の説明がある。
私は現在カタカナと呼ばれている文字は漢字伝来以前から日本に存在していた文字であると考えている。
「片仮名」は当て字であり、本来の意味からすると、「堅金文字」「堅鉋文字」「刀文字」である。
古来から日本人は日本独自の大工道具である槍鉋(やりがんな)を使って木材を加工してきた。
堅い石に槍鉋で独自の文字を刻んだ。
大分県などで古代文字が刻まれた天然石が江戸時代に見つかっている。
楔形文字の例を出すまでもなく、石に文字を刻む場合、ひらがなのようなくねくねした文字では刻むことはできない。
カタカナのように直線だけで構成される文字が適しているのである。
古代の筆記用具は、天然石と槍鉋だったので、その知識と技能を併せ持った人だけが文字を書くことができた。
現代人の私がカタカナを見ると、カクカクとしていて何か異形のような特別な感覚を受ける。
特に「ウ」という文字は一画目は点ではなく上から下に下ろす線であるのが漢字やひらがなにはない特異なことなのだ。
プログラマにとって、カタカナは1バイト文字しか扱えなかった時代に「半角カタカナ」というフォントが活躍した時代の記憶が強い。
現在でも一部の公共システムや銀行システムでのみ使われ続けている。
アルファベットと同じ小さな領域に日本語をフォントとして実装するには、漢字やひらがなでは難しく、カタカナがもつ直線性や簡易性が大きく役立ったのである。
日本が平安時代になり、多くの人々が「毛筆と紙」という筆記用具を用いるようになり、カタカナが持つ直線性は筆では書きづらいため、万葉仮名を経由して「ひらがな」を使うようになったのである。
カタカナがひらがなより先に成立していたことは遺物から明らかで、ひらがなが万葉仮名を経て成立したことも遺物から明らかなことである。
・似ている文字
う、え、か、き、こ、せ、も、や
ウ、エ、カ、キ、コ、セ、モ、ヤ
・全く同じ文字
へ、り
ヘ、リ
このように、ひらがなとカタカナは似ている文字が非常に多い。
普通に考えると、
万葉仮名 → ひらがな → カタカナ
という成立過程をたどったのだろうと考えるのが普通だろう。
しかし、実際には、
カタカナは突然成立し、
ひらがなは万葉仮名から成立したのが実際だ。
ほんとうにカタカナというのは不思議な文字なのである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち