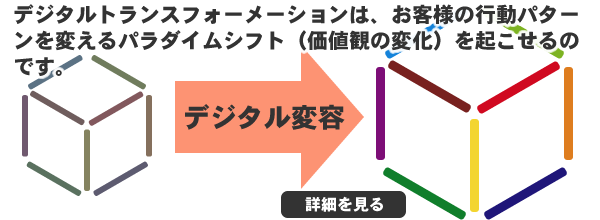景気減速と景気回復の流れ〜80年代バブルからバブル崩壊そして10年代景気浮揚まで
2000年ごろからだろう。
ホリエモンがマスコミでもてはやされ、
企業というのは利益を最大化させ株主様に配当として還元することが企業の使命であるともっともらしく話している光景が思い出される。
買収を繰り返し、企業が拡大することが良いことだと。
確かに、企業とは理念や技術力をもつ人に資産は持っているが自分では事業を行う力のない人が投資し、資産家は利益を搾取するということから始まったものだ。数百年も昔の話だ。
その後、銀行という仕組みができあがり、特定の資本家に依存せずに、技術や理念を持つ人が事業を興すことができるようになった。
そして、企業とは人と人が協力して一人ではできない事業を行う素晴らしい仕組みとなった。
しかし、多くの企業が株式市場に上場するようになり、企業の不正が多発することを要因として、企業の情報公開が求められ、売り上げよりも純利益を追求するように変わった。
本来、企業は利益を出す必要は全くない。
売り上げをあげて、そこから社員に給与を支払う。
それでも余れば、企業に寄与した度合いによって、社員にボーナスを支払う。
銀行は企業に融資し、利子を受け取れればよい。
そこに、MBAや海外本に書かれたことを鵜呑みにして、「企業は株主のために存在している」なんていう間違った認識が広がることになった。
最終利益を最大化するためには、コストの最たるものである人件費を削減すればよいという短絡的な考えに陥った企業は80年代以降、東南アジア諸国など海外に工場を移転し、現地の安い人件費でモノを生産して日本に輸入するという施作をとることが良いことだとされるようになった。
その結果、日本国内は安い商品であふれ、90年代そして0年代と20年にも渡って、日本の失業率はあがり、給与は低下し続けた。
10年代になり、円をG7諸国並みに社会に供給するというアベノミクスにより為替が適正化されると、企業は国内に工場を戻し、パソコンさえも国内で生産されるようになった。
生産が国内に戻ることにより、給与低下に代表されるデフレは解消し景気は浮揚した。
<景気減速と景気回復の流れ 80年代バブルからバブル崩壊そして10年代景気浮揚まで>
80年代の為替変動(プラザ合意)
円高
↓
生産の海外移転
↓
失業者増加
給与低下
↓
景気減速
↓
非正規雇用だけが微増
↓
さらに景気悪化
↓
10年代に円をG7諸国並みに社会に供給(アベノミクス実施)
↓
円安ドル高
↓
国内に生産拠点が戻る
↓
失業率低下
給与増加
↓
景気回復
↓
人不足
さらに給与増加
要するに、国内景気は何によって決定するのかと言えば、国内で消費するモノは国内で生産することだ。
一見すると、為替が原因で景気が下がったり上がったりするように見えるが、そうではなく、日本で消費するモノの生産拠点が国内か海外かが景気を左右してきたのだ。
一企業が利益を追求すると、米国で稼いだ資本を元手に、メキシコなどの人件費が安い海外に生産拠点を移し米国に輸出すれば、その企業は儲かる。
しかし、海外に工場が移転すると、米国などの先進国では失業者が増え、給与は低下する。
米国では治安が悪化し、米国人は不幸になる。
私はドナルドトランプの「米国で売りたければ米国の工場で生産しろ」という主張はとても正しいと思うのである。
企業は海外への輸出や海外生産からの輸入で利益を上げることをやめ、現地生産現地消費を徹底すべきだ。
企業の売り上げが世界一になっても、企業の規模が世界一になっても、その国の人々が幸せにならなければ、何の意味があるだろう。
企業とは人が幸せになるために人が作りしものだからだ。
-
日本は輸出で生きてきたとか輸出企業が日本を支えているみたいな主張をする人がいるが、超一流の先進国になった今では輸出は全くGDPには影響がない。(全輸出のGDPに占める割合は数%程度)
企業ではなく、日本人が幸せになるためには、現地生産現地消費を徹底すべきなのである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち