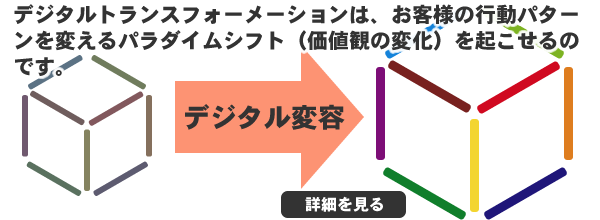本屋は小学生の私にとって知識探求の始まりだった
子供ころ過ごした家の隣はいろんな薬や化粧品が置いてある薬局で、新聞屋、呉服屋、野菜やコカコーラやファンタの置いてある若菜商店、少し外れたところにレコードが並ぶ牛越し電気店と、呼び鈴を鳴らすと100メートルぐらい先からおばあさんが鍵を開けにやってくる駄菓子屋が並んでいて、右隣には変わった金魚が泳ぐ水槽のある床屋、店主が変わるごとに美味しさも変わった札幌ラーメン屋、マロンケーキが好きになったケーキ屋、それに銀行があった。
県道を挟んだ向かいには、農協、お茶屋、釣り道具屋、金魚を売っているお店、金物屋、お大師様と呼ばれてた宗教施設、清酒をよく買いに行ったかやの商店が並んでいた。
そんな小さな商店街で私は高校生まで過ごしたのだが、小学生のとき薬局の隣にあすなろ本屋ができた。
本屋ができる前にそこに何があったのか記憶がない。
そのころ、近くのお大師様のお姉さんが先生になっていた寺小屋に行くことになった。
その寺小屋では市販のドリルをひたすら解かされるような授業形態だったので、寺小屋には行かずにそのころできたばかりの本屋に入り浸っていた。
子供用に書かれた世界の軍艦だとか、ツタンカーメン王の秘密だとかそんな類のハードカバー本を座り込んで何時間も読んでいた。
寺小屋をサボる時以外も暇があれば本屋に行っては本屋のおじさんやおばさんが座っているすぐ横の棚に置いてあるトイレット博士やマカロニほうれん荘、ナナハンライダーなどの漫画単行本を数時間読んでいることがよくあった。
商店街のどのお店に行っても、スーパーマーケットのように人がたくさんいるということはなかった。
本屋でも、私が立ち読みしている間、ほとんど他の客はいなかったと思う。
私の家は旧家だったこともあったのか、私も時々は本を買っていたので、文句を言われることは一度もなかった。
そんな幼少期の体験があったためなのか、暇があれば本屋で立ち読みしたり図書館で立ち読みしたりするのが習慣になった。
専門書を探したい時にはよく神保町の三省堂や書泉グランデで一日中うろうろしていた。
数年ほど前から、新書で買いたいものがある時以外は本屋に行かなくなったし、移動中の駅ビルで本屋を見かけても立ち寄ろうとさえしなくなった。
専門的なことがらでも、新規的な新聞でもiPadで探して読むように変わった。
本屋とは私にとってこの社会や特定分野に関する情報を収集する場であり、本屋は小学生の私にとって知識探求の始まりだった。
知識探求の場が本屋からiPadに変わってしまったのだ。
インターネットは無料だという間違った認識があるが、インターネットは毎月数千円の利用料金を誰もが払っている。
実は、情報を共有するためにみんなでお金を出し合って太平洋に光ファイバーを敷設したりしているのである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち