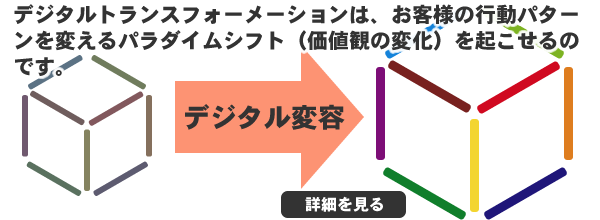VR体験の芸術娯楽への影響
芸術や娯楽がどのように変遷してきたかをまとめてみる。
<芸術や娯楽媒体の変遷>
面白い人や出来事(家、部落、非営利)→劇団、劇場(組織化、資本、営利)→ラジオ、映画館(広告モデル、コピーを配布)→テレビ→インターネット(消費者が放送・出版の主体)→VR(臨場感体験、リアルとバーチャルの判別不能)
上図を見てもらうと分かるように、娯楽が複製されたものを一般に配布するようになると、臨場感を喪失していった。
複製品(コピー商品)が「ホンモノ」を上回ることはできないように、インターネット上の娯楽が面白い人や面白い出来事を上回ることは到底できないのだ。
この先、VRによって我々は臨場感を取り戻すことになる。
そして、現実か非現実かはその場にいる人にとって人間の五感で判別ができなくなるだろう。
実体験と全く同様の体験(筋肉の動き、心の動き)をすることができるようになるので、あることを体験することに対する敷居がとても低くなる。
その結果、プログラムされた体験によって成長していく人間ができあがる。
その人間は人間と言えるだろうか? 体や見た目は人間でも、もはやヒューマノイドではないか?
チャンスに恵まれているものは苦労して「ホントウの現実」をその場に出向いて体験する数少ない人たちも存在はするだろうが、人類の1パーセントにも達しないだろう。
そうなると、人は「人生とはゲーム」を地でいく人生を歩むことになる。
プログラムされた山登りを体験し、プログラムされた接吻や性体験を体験し、机上の空論ではなくVR上の現実でその人間は人間となっていくのだ。
完全に画一化された体験(ABCDEFGの選択肢からどの山にするかを選ぶぐらいの自由しかない)を人間全員がすることになる。
ゲームとは言っても、感情や筋肉運動、心肺機能は実際にその人が持つ知力や体力を使って行う。
一部はゲームセンターのような施設に行って体験する必要があるが、徐々に家庭内ですべての体験が行えるようになるだろう。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち