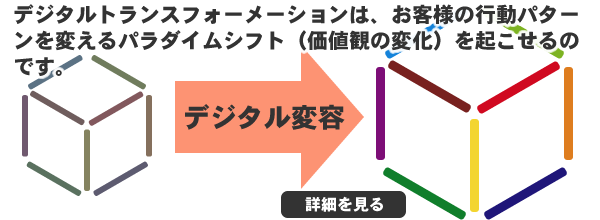1991年の春に私がコンピュータについてサカイ先生から最初に教えてもらったこと
1991年の春に、私がコンピュータについてサカイ先生から最初に教えてもらったのはコンピュータという機械は二進数で考えるということと、バイトとワードの概念だったと思う。
バイト(byte)というのは「ひと噛み」という意味がありIBMが考え出した概念で最小単位の二進数の一桁を表すビット(bit)が8個集まったものだ。
アルファベット数字その他記号を合わせて256通りの意味づけができる集まりを論理的な最小単位として定義したのである。
ワード(word)とはSoCsにあるCPUがもつレジスタと呼ばれる演算用メモリの大きさを表すものだ。
要するにCPUが1クロックで演算する対象の大きさであり、四則演算を始めとするあらゆる演算はワード単位に行われることになる。
64ビットと旧型の32ビットの違いはこのレジスタの大きさのことであるので、一度に演算できるデータ量が倍違うということだ。
データ量は二倍しか違わなくてもメモリアドレス空間で考えると10億倍の大きさの違いとなるのだ。
このCPUとメモリや周辺機器類を結ぶのがバスと呼ばれる配線だ。
この銅線もスピードと一度に転送できるデータ量が上りと下りで決まっている。
CPUは物理的にあるいは静的に演算の種類とその役割が定義されていて、PC(プログラムカウンタ)が指し示すメモリアドレスから命令とデータを読み込んで演算を繰り返す。
この演算の種類定義をARMやMIPSがライセンス販売しているものだ。
コンピュータとはこれだけのもので、bluetoothとかUSB3とかwifiとかretina displayなどと言ってるが、これらは単に周辺機器とCPUとのやりとりの約束事を定義しているにすぎないので重要ではない。
iOSやandroidやlinuxなどをOS(オペレーティングシステム)と呼ぶが、これらは単にCPUが提供しているマルチスレッドを始めとする各種機能を使っているにすぎない。
OSの一番の目的はCPUが提供する機能をブレークダウンし利用者とアプリが簡単にコンピュータを利用できるような環境を提供することにあり、それ以上でも以下でもないのである。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち