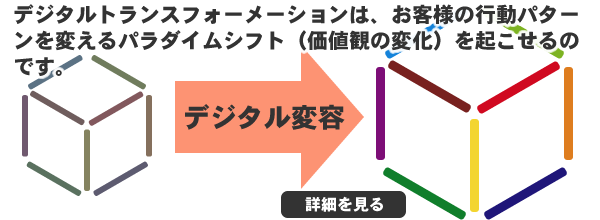インドの人やアラブの人が自分たち独特の英語で話しているように、私たち日本人は「日本人が話す英語としての英語」で良いのだ
英語を勉強したくなったのは、高校2年のときのテレビコマーシャルで Scarborough Fair を聞いたときだった。
その歌詞を辞書を調べながら味わったものだ。
20歳の頃、六本木周辺で働いていたとき、モデルのような外国人の女性に「乃木神社はどうやっていくの?」と訊かれた。
私は、Nogi shrine の shrine の意味がわからず 「シュライン?」とおうむ返しすると、その女性は「じゃいいわ」みたいな感じで去って行ってしまった。
初めて外国人に話しかけられて嬉しかったんだけど、ほろ苦い思い出になった。
中学、高校と習った教育としての英語は単語と熟語の意味を覚えるのに汲々としていた。
その後は、場面ごとによく使うフレーズを覚えてしまえばいいんだとか言われたこともあった。
私は暗記が大の苦手なので、年号を覚えさせられる日本史や世界史が大嫌いだったほどなので、英語も得意ではなかったけれど、嫌いにならずに済んだ。
-
かれこれ10年以上経つだろうか。
NHKのマジカル英会話という番組を見たことで英語に対する考え方が大きく変わった。
英単語というのはそのセンテンスによって意味が変わり、動詞ならその次にくる接続詞や副詞によって意味が変化すると教えられてきたしそう思っていた。
暗記のできない私には一生かかっても全てのイディオムを覚えるなんてことは到底無理なのだから、英語で会話できるようになるなんてのは無理だと。
そう思ってきたが、話を聞いてみると、ネイティブスピーカーは接続詞も含めて単語ごとにイメージを持っていて、場面やセンテンスごとにそのイメージにあった単語を並べているだけなのだということを知った。
「そうか、英語を話すには頭の中を外国人にすればいいんだ」とひらめいた。
日本語で考えるんじゃなくて、英単語で考えること。
そのためには、「各単語の意味を記憶する」のではなく「各単語がもつなんとなくのイメージを身につける」ようにすることなのだと。
このことは目からうろこが落ちるぐらいの衝撃だった。
学校では誰も教えてくれなかったからね。
今でも、難しい英単語やネイティブが使う言い回しは分からない。
言葉は変化するものだしね。
中学校で教わった
is (was, were)
take
get (got)
have (has, had)
を使えばセンテンスは出来上がる。
あとは、ネイティブの話し方のクセを押さえれば良い。
天気や時間なら
it's
をネイティブは使いたがるとか
話しかけるときは
would youcould you
may i
なんかをネイティブはよく使っているとかいうことを押さえれば良いんだ。
私たちはネイティブスピーカーではないのだし、海外に長期留学できるような資本もないのだから、ネイティブのように話せなければダメだとか思わずに、インドの人やアラブの人が自分たち独特の英語で話しているように、私たち日本人は「日本人が話す英語としての英語」で良いのだと思っている。
| 2023年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
iOS
web
アプリの著作権
ブロックチェーン/暗号技術
新しい社会
禅・大乗仏教
日本のなりたち